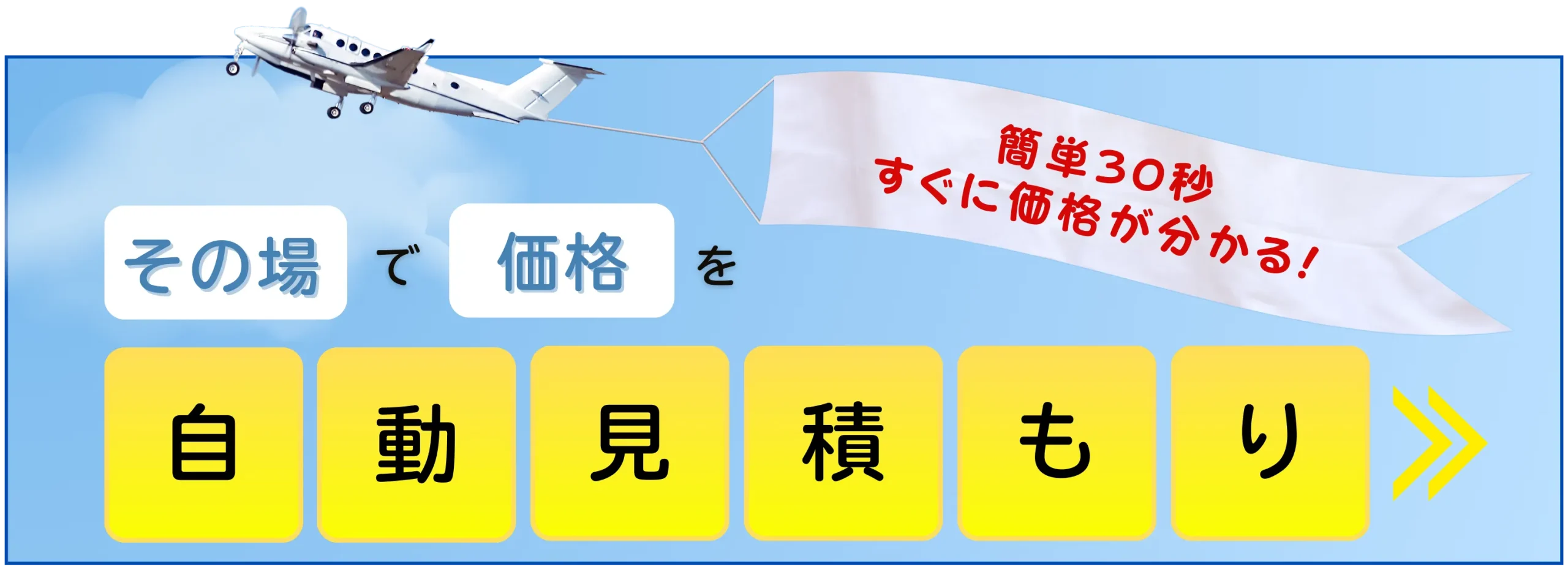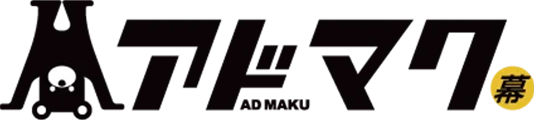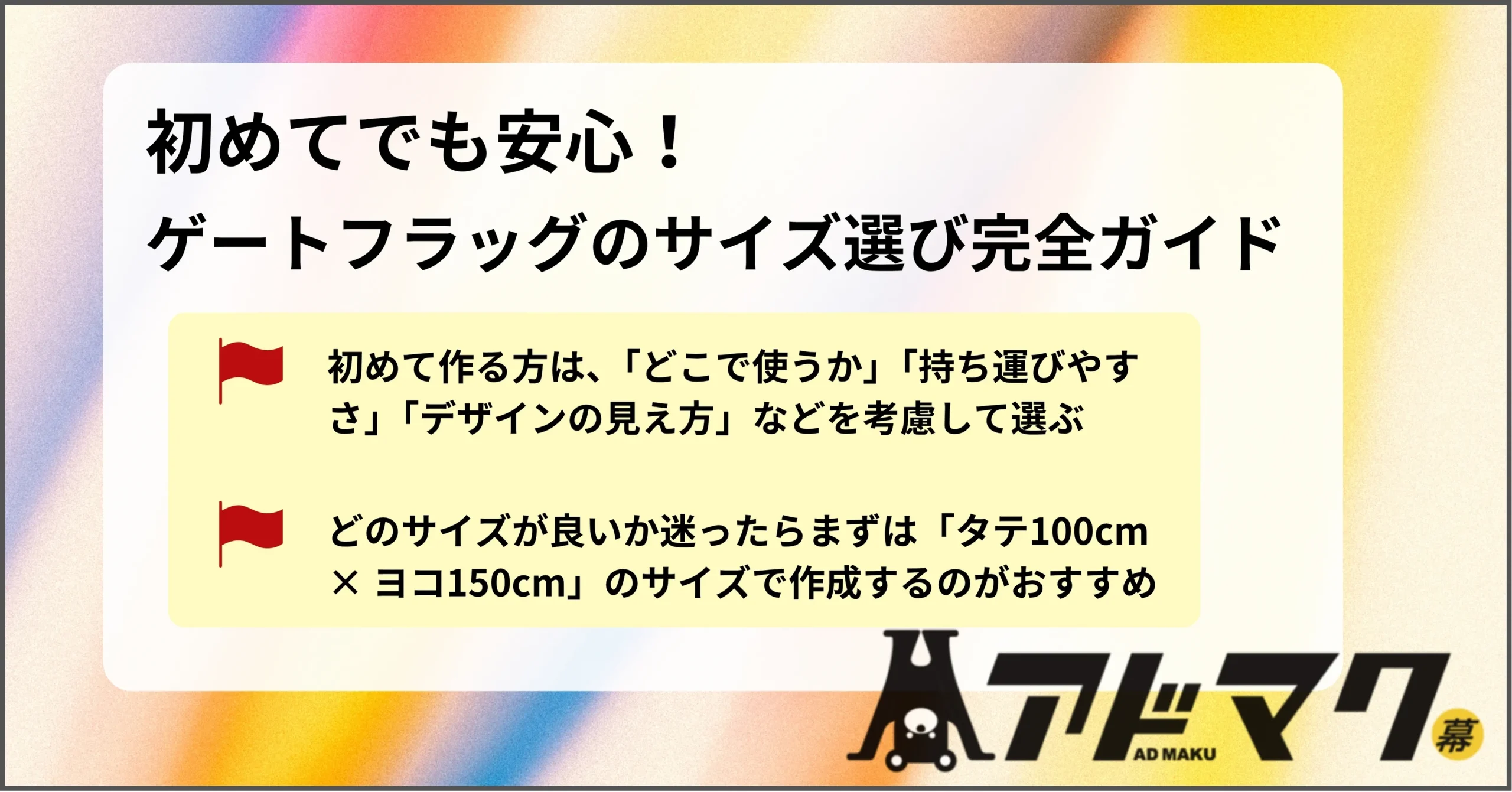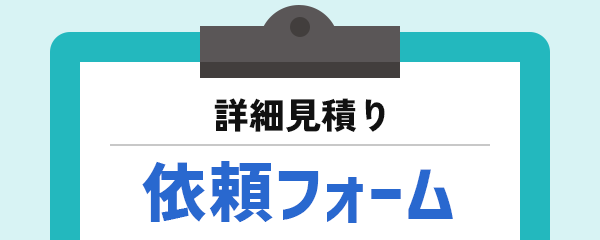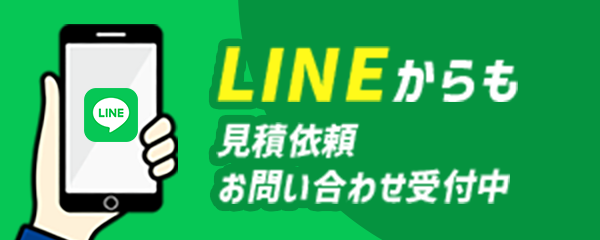応援するチームのためにゲートフラッグ(通称:ゲーフラ)を作ってみたいけれど、「どのサイズにすればいいのか分からない…」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?実は、サイズ選びで失敗しないために一番大切なのは、「どこで使うか」と「スタジアムのルール」を事前に把握しておくことです。本記事では、初めての方でも迷わず選べるよう、ゲートフラッグの一般的なサイズから観戦場所別のおすすめサイズ、Jリーグの規定や価格相場まで、丁寧に解説しています。
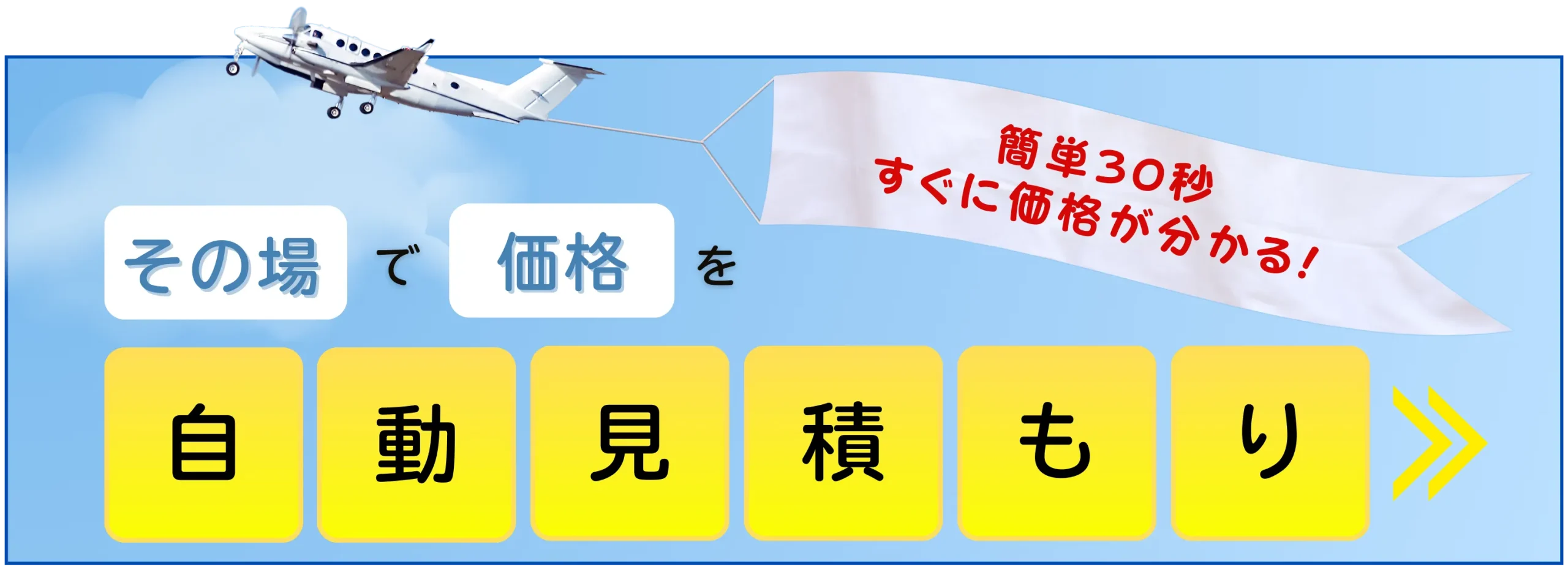
目次
ゲートフラッグの基本サイズを知ろう!
ゲートフラッグのサイズはどれくらいが一般的?サイズ一覧
ゲートフラッグには決まった規格があるわけではなく、様々なサイズで作成されています。ここでは、制作会社などでよく取り扱われている一般的なサイズを一覧にまとめました。それぞれの特徴を把握し、自分の作りたいイメージに近いサイズを見つけてみましょう。
| サイズ(縦×横) | 特徴 | 主な用途・メリット |
| 約60cm × 90cm | 小型サイズ | 手軽に持てる大きさで、お子様や女性にも扱いやすい。混雑した場所でも掲げやすいのが魅力。 |
| 約90cm × 90cm | 正方形サイズ | 扱いやすさとデザインの見やすさのバランスが良い。初心者でも扱いやすく、人気のある形状。 |
| 約100cm × 150cm | 中型・定番サイズ | 最も一般的なサイズ。デザインの迫力と持ち運びやすさを両立しており、多くのスタジアム規定に対応しやすい。 |
| 約120cm × 180cm | やや大きめサイズ | 定番サイズより一回り大きく、より目立たせたい場合におすすめ。ただし、スタジアムによっては規定を超える可能性も。 |
| 約150cm × 225cm | 大型サイズ | 非常に迫力があり、ゴール裏などで掲げると壮観。持ち運びや掲出には注意が必要で、クラブの規定確認が必須。 |
初心者におすすめの定番サイズはこれ!
もし、どのサイズにすれば良いか迷ってしまったら、まずは「タテ100cm × ヨコ150cm」のサイズで作成するのがおすすめです。
このサイズが初心者の方におすすめな理由は、以下の3つです。
- 扱いやすさ:大きすぎず小さすぎないため、一人でも比較的簡単に掲げることができます。持ち運びの際も、大きすぎるサイズに比べて負担が少ないです。
- 視認性:選手名やエンブレム、メッセージなど、伝えたいデザインをしっかりと表現できる大きさです。スタンドからでも十分認識できます。
- 規定への対応:多くのJリーグクラブが定めるサイズ規定内に収まりやすい大きさです。スタジアムに持ち込めないという失敗のリスクを減らせます。(※ただし、最終的な確認は各クラブの公式サイトで必ず行ってください)
まずはこの定番サイズでゲートフラッグ作りの楽しさを体験し、慣れてきたら2枚目以降で異なるサイズに挑戦してみるのも良いでしょう。
【利用シーン別】ゲートフラッグにおすすめのサイズの選び方!
スタジアムの観戦場所でサイズを選ぶ
ゴール裏で掲げる場合のおすすめサイズ
熱狂的なサポーターが集まるゴール裏は、チームを鼓舞する応援の中心エリアです。ここでは、選手たちにしっかりとメッセージが届くよう、比較的大きなサイズのゲートフラッグが好まれます。ただし、周りのサポーターの視界を妨げないよう、掲げるタイミングやマナーには配慮が必要です。
| サイズ感 | 具体的なサイズ例(横×縦) | 特徴・注意点 |
| 大きめ | 120cm × 100cm 以上 | 選手からの視認性が高く、力強い応援を表現できます。重量があるため、頑丈なポールが必要です。掲げた際に周囲の迷惑にならないか確認しましょう。 |
| 標準 | 100cm × 80cm 程度 | ゴール裏で最も一般的なサイズです。扱いやすさとアピール力のバランスが良く、初心者の方でも安心して使用できます。 |
スタンド席で掲げる場合のおすすめサイズ
メインスタンドやバックスタンドなどの指定席で観戦する場合、自分の座席スペース内で扱えるコンパクトなサイズが基本となります。特に、前の席の人の頭に当たったり、隣の人の視界を遮ったりしないよう、周囲への配慮がゴール裏以上に求められます。
| サイズ感 | 具体的なサイズ例(横×縦) | 特徴・注意点 |
| 標準 | 90cm × 70cm 程度 | 自分の座席の幅に収まりやすく、扱いやすいサイズです。試合中ずっと掲げるのではなく、選手紹介や得点時など、ピンポイントで掲げるのに適しています。 |
| 小さめ | 70cm × 50cm 以下 | 子どもや女性でも軽々と扱えるサイズです。混雑した場所でも迷惑になりにくく、手軽に応援の気持ちを表現したい方におすすめです。 |
持ち運びやすさを重視したサイズ選び
公共交通機関を利用してスタジアムへ向かう方や、アウェイ遠征に頻繁に参加するサポーターにとって、持ち運びやすさは重要な選択基準です。ゲートフラッグ本体のサイズはもちろん、ポールを収納した際の大きさも考慮しましょう。分割式のポールを選ぶと、大きな旗でもコンパクトに持ち運べます。
移動の負担を減らしたい場合は、一般的に「横100cm × 縦80cm」以下のサイズがおすすめです。このサイズであれば、旗を畳んだときに多くのスポーツバッグやリュックサックに収まりやすく、ポールも短めのものを選べます。
デザインの細かさでサイズを決める
ゲートフラッグに描きたいデザインによっても、最適なサイズは変わってきます。デザインの視認性を確保するために、描く内容に合わせた大きさを選びましょう。
- 細かいデザインの場合(選手の写真、複雑なイラストなど)
デザインのディテールをしっかり見せたい場合は、ある程度の大きさが必要です。特に選手の顔写真などを使う場合、小さいサイズでは表情が潰れてしまい、誰だか分からなくなってしまう可能性があります。「横120cm × 縦100cm」以上の大きめサイズを選ぶと、デザインの魅力が伝わりやすくなります。 - シンプルなデザインの場合(大きな文字、単純なエンブレムなど)
太いフォントの文字や、シンプルな図形がメインのデザインであれば、比較的小さなサイズでもスタジアムで十分に目立ちます。「横90cm × 縦70cm」程度のサイズでも、力強いメッセージを伝えることが可能です。
要注意!スタジアムごとのゲートフラッグのサイズ規定とは?
Jリーグの基本的なサイズルール
Jリーグでは、すべての試合で適用される「Jリーグ試合運営管理規程」という統一ルールを設けています。この中で、応援に使う旗(フラッグ)に関する基本的な指針が示されています。
特に重要なのが、通称「Lフラッグ」と呼ばれる大旗の扱いです。具体的には、メインポールが1本で、旗の大きさが「縦1,015mm×横1,575mm」を超える旗は「大旗」と定義され、原則として指定されたエリア(主にゴール裏の応援エリア)以外での使用が禁止されています。このサイズは、市販されているLフラッグ(約100cm×150cm)が基準となっています。
つまり、この基準サイズ以下のゲートフラッグであれば、多くのスタジアムのスタンド席でも使用できる可能性が高いと言えます。ただし、これはあくまでJリーグ全体の基本ルールです。安全なスタジアム運営のため、各スタジアムがより厳しい独自のルールを設けている場合があることを必ず覚えておきましょう。
各クラブの公式サイトでの規定確認方法
ゲートフラッグを確実にスタジアムで使用するためには、観戦に行くスタジアムのルールを個別に確認することが不可欠です。特にホームゲームだけでなく、アウェイゲームに遠征する際は、相手クラブの公式サイトを事前にチェックしましょう。
確認方法は以下のステップが一般的です。
- 観戦予定のクラブの公式サイトにアクセスする
まずは、ホームクラブまたはアウェイ先のクラブの公式ウェブサイトを開きます。 - 「観戦ルール」「スタジアム」「試合情報」などの項目を探す
サイト内のメニューから、「観戦ルール・マナー」「スタジアムアクセス」「〇〇スタジアムでの応援について」といった案内ページを探します。 - 応援アイテムや掲出物に関する規定を確認する
ページ内に「応援バナー・横断幕・旗類の掲出について」「持ち込み禁止物」などの項目があります。そこで、ゲートフラッグ(大旗、フラッグ類)のサイズ、ポールの材質や長さ、掲出可能な場所などが詳細に記載されています。
クラブによっては、旗のサイズだけでなく、2本以上のポールを使うもの(横断幕と見なされる場合がある)や、ポールの材質(塩化ビニール製のみ可など)についても細かく規定していることがあります。制作を依頼する前に、必ず最新の情報を公式サイトで確認する習慣をつけましょう。
どれくらい違う?サイズ別ゲートフラッグの価格相場をチェック!!
サイズ別の料金相場
ゲートフラッグの価格は、サイズが大きくなるほど高くなるのが基本です。持ち運びやすいコンパクトなものから、ゴール裏で目立つ巨大なものまで、代表的なサイズの価格相場を一覧にまとめました。
| サイズ区分(目安) | 具体的な寸法例 | 価格相場 |
| Sサイズ | 横90cm × 縦60cm | 5,000円~10,000円程度 |
| Mサイズ | 横150cm × 縦100cm | 10,000円~20,000円程度 |
| Lサイズ | 横200cm × 縦150cm | 20,000円~30,000円程度 |
| LLサイズ以上 | 横300cm × 縦200cm~ | 30,000円~(要見積もり) |
※上記は片面印刷の場合の一般的な価格帯です。両面印刷や特殊な生地を選ぶと、価格はさらに上がります。正確な料金は、必ず制作業者の公式サイトで確認したり、見積もりを依頼したりしてチェックしましょう。
費用を抑えるためのサイズの工夫
「少しでも安くゲートフラッグを作りたい!」という方は、サイズの決め方を工夫することで費用を抑えられる可能性があります。単純にサイズを小さくする以外にも、知っておきたいポイントがいくつかあります。
一つ目の方法は、「生地の規格サイズ」を意識することです。ゲートフラッグに使われる生地には、元となる大きなロールの幅(規格)があります。この規格幅から無駄なく生地を切り出せるサイズで注文すると、特注サイズよりも価格が安くなるケースがあります。例えば、150cm幅の生地なら、縦横150cm以内のサイズで調整するといった工夫です。業者によっては推奨サイズや格安サイズを提示している場合もあるので、見積もり時に確認してみるのがおすすめです。
二つ目の方法は、作りたいサイズから「少しだけ小さくする」ことです。例えば「横200cm × 縦150cm」で検討している場合、それを「横195cm × 縦145cm」のように数cm小さくするだけで、使用する生地の量や印刷の都合で料金が変わることがあります。希望のサイズ感と予算を業者に伝え、「この予算内で作れる最大サイズはどれくらいですか?」と相談してみるのも有効な手段です。
Q&A|ゲートフラッグのサイズに関するよくある質問
ここでは、ゲートフラッグのサイズに関して、初心者の方が抱きがちな疑問にお答えします。製作前に疑問点を解消して、安心してゲートフラッグ作りを始めましょう。
規定サイズギリギリでゲートフラッグを作るのは危険ですか?
結論から言うと、スタジアムの規定サイズ上限ギリギリでゲートフラッグを製作するのは、あまりおすすめできません。万が一のことを考え、縦横それぞれ数cm程度の余裕を持たせたサイズで設計するのが安全です。
その理由は主に2つあります。
- 製作時の誤差:布を裁断したり縫製したりする過程で、設計したサイズからわずかな誤差が生じることがあります。手作りでも業者への依頼でも、数cmのズレは起こり得ます。
- 当日の計測誤差:スタジアムに持ち込む際、係員の方がメジャーでサイズを計測します。その際の測り方によっても、わずかな誤差が出る可能性があります。
もし規定サイズを1cmでも超えてしまうと、スタジアムへの持ち込みが許可されず、せっかく作ったゲートフラッグが使えなくなる可能性があります。悲しい思いをしないためにも、規定サイズよりも少し小さめに作ることを心がけましょう。
旗のサイズとポールの長さはどうやって合わせればいいですか?
ゲートフラッグを掲げるためのポールは、旗のサイズに合わせて適切な長さを選ぶ必要があります。一般的には「旗の縦の長さ(短い辺) + 持ち手部分(20cm〜30cm程度)」がポールの長さの目安となります。
持ち手部分が短すぎると掲げにくく、長すぎると扱いにくくなるため、自分の体格や持ちやすさに合わせて調整するのがポイントです。以下にサイズの目安をまとめました。
| 旗のサイズ(縦×横) | 推奨されるポールの長さ |
| 80cm × 120cm | 約100cm 〜 110cm |
| 100cm × 150cm | 約120cm 〜 130cm |
| 135cm × 200cm | 約155cm 〜 165cm |
ポールはホームセンターなどで手に入る塩ビパイプを利用するのが一般的です。実際にパイプを握ってみて、太さや長さを確認してから購入すると失敗がありません。
ゲートフラッグのサイズ以外に注意する作成ポイントはどこですか?
ゲートフラッグを製作する際は、サイズの他にもいくつか注意すべき重要なポイントがあります。ルールを守って、気持ちよく応援するために必ず確認しておきましょう。
- 素材の選定:軽くて振りやすい「ポンジ」や、厚手で発色の良い「トロマット」といった生地がよく使われます。スタジアムによっては「防炎加工」が必須の場合もあるため、観戦するクラブのルールを確認しましょう。
- デザインのルール:選手やクラブを応援する目的から逸脱した、誹謗中傷、政治的・差別的なメッセージ、広告宣伝活動とみなされるデザインは禁止されています。デザインがルールに抵触しないか、事前にクラブの観戦マナーやガイドラインをチェックすることが不可欠です。
- ポールの材質:多くのスタジアムでは、安全上の理由から金属製のポールや角材などの硬い素材の持ち込みが禁止されています。一般的には、軽くてしなる塩化ビニール(塩ビ)製のパイプが推奨されています。
これらのポイントも、ゲートフラッグのサイズ選びと同じくらい重要です。製作を始める前に、必ず応援するクラブの公式サイトで最新の情報を確認してください。
まとめ
アドマクではオリジナル横断幕・懸垂幕・垂れ幕のデザイン制作を承っております。ご利用用途やサイズから費用を自動見積もりをすることもできますので、ぜひご確認ください!