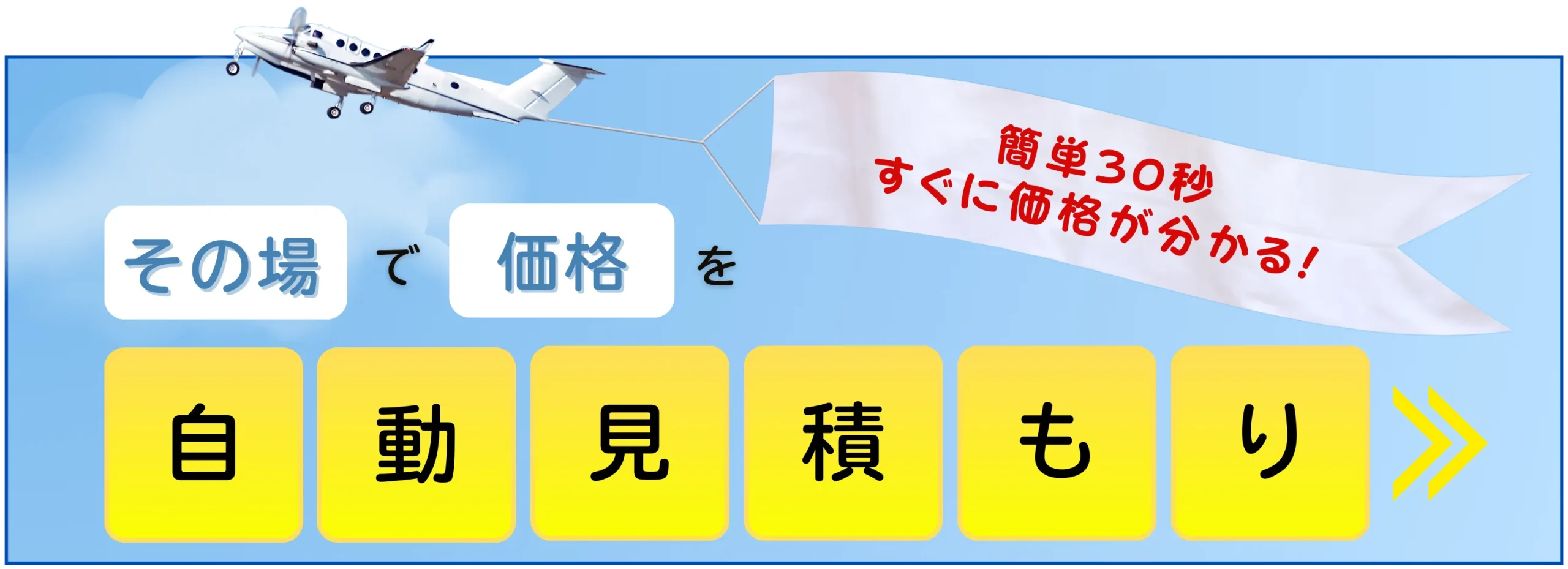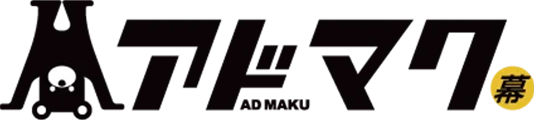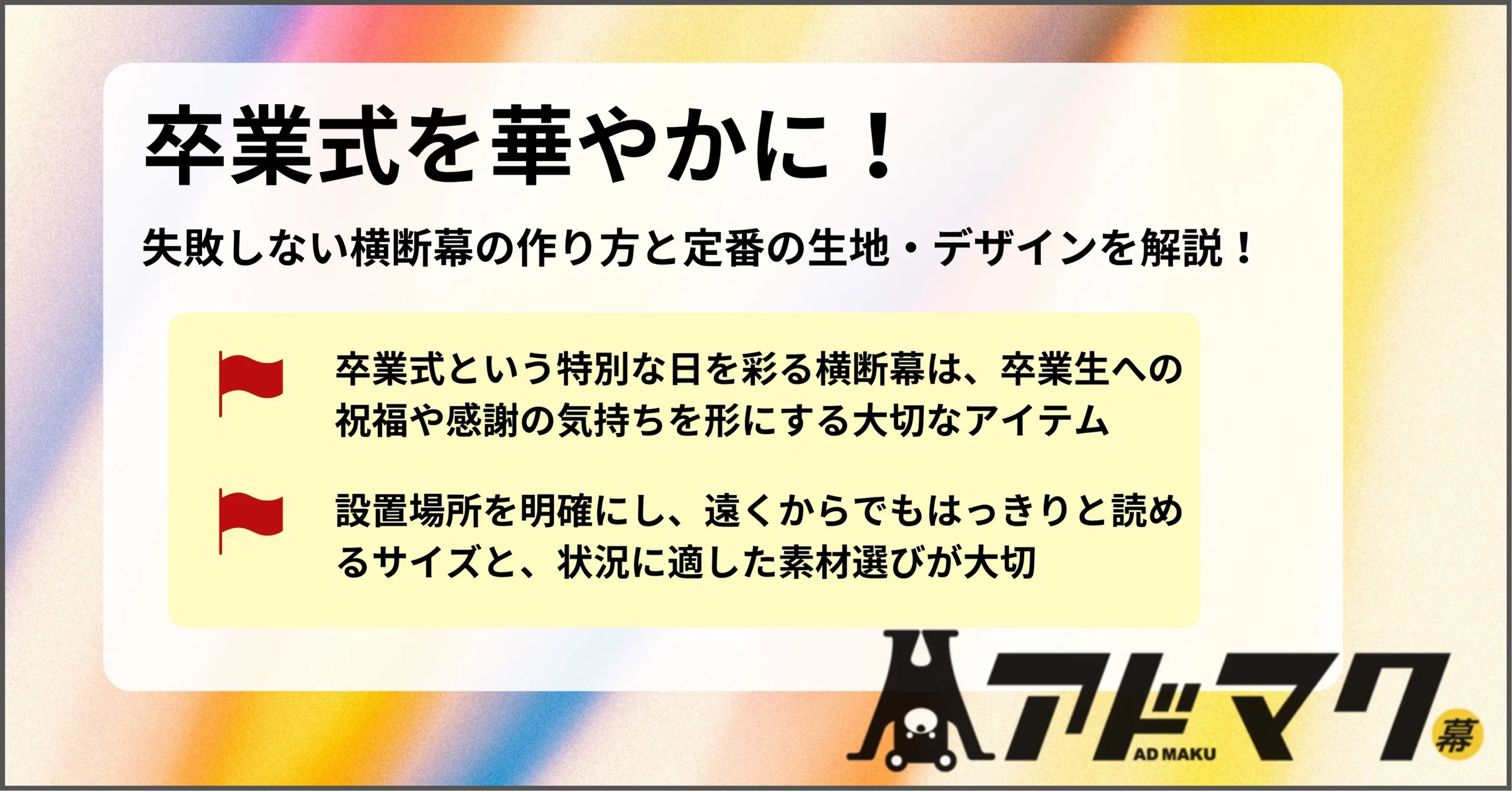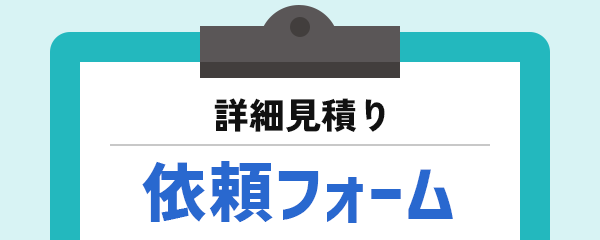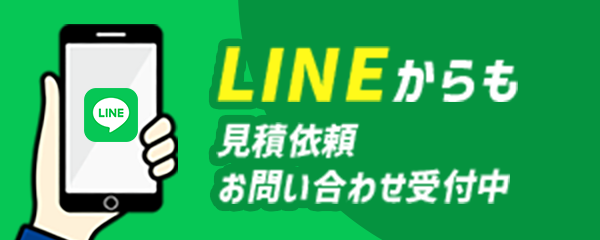卒業生の門出を祝う大切な卒業式。心に残る横断幕で華やかに送り出したいと考えている保護者の方や先生も多いのではないでしょうか?しかし、いざ作ろうとすると「どんなサイズやデザインにすればいいの?」など、様々な疑問が浮かびますよね。本記事では、そんなお悩みを解決するため、卒業式の横断幕作りで失敗しないためのポイントを網羅的に解説します。最適なサイズ・レイアウト・フォントの選び方から、定番の生地、業者依頼と手作りの流れ、当日の安全な設置方法まで、この記事を読めば横断幕の準備に関する全てがわかります。この記事を参考に、感動的な卒業式を演出する最高の横断幕を準備しましょう。
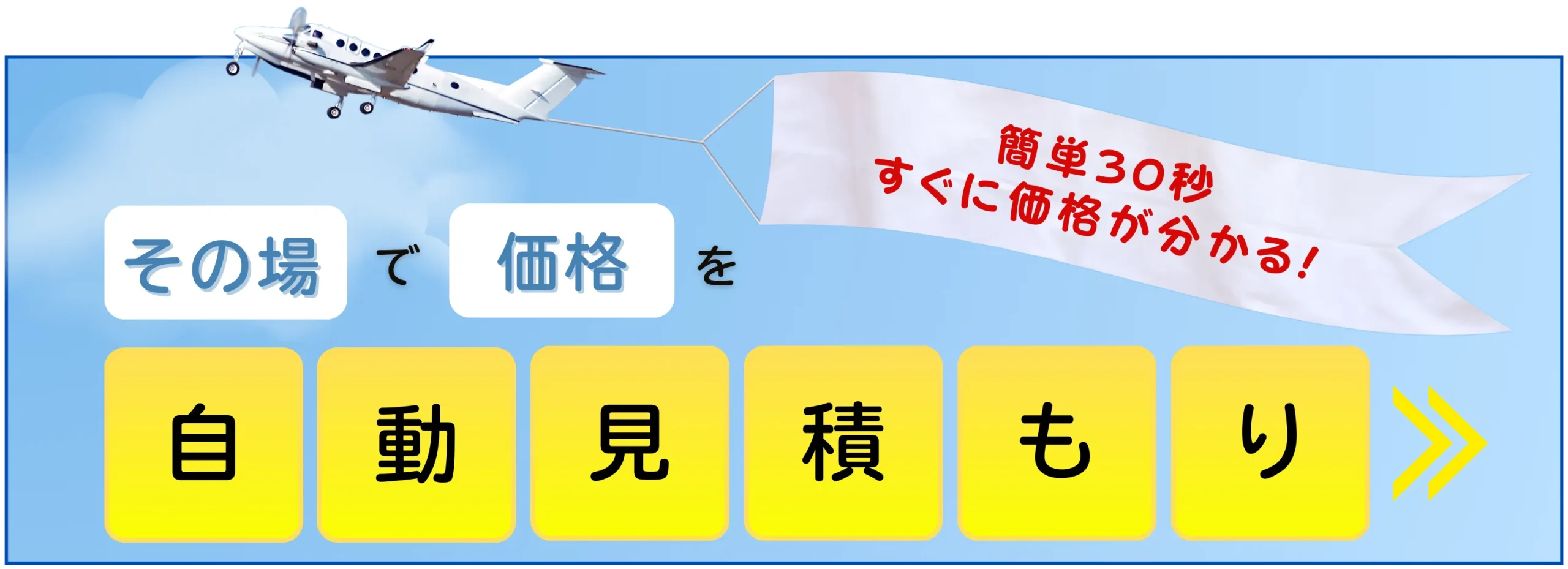
目次
失敗しない横断幕の作り方!サイズ・レイアウト・フォントの選び方
卒業という晴れの舞台を彩る横断幕。心のこもったメッセージを卒業生に届けるためには、デザインの基本となる「サイズ」「レイアウト」「フォント」の3つの要素が非常に重要です。
ここでは、失敗しないための具体的な選び方のポイントを解説します。
横断幕のサイズ選び!設置場所と見やすさのバランスとは
横断幕のサイズは、設置する場所と、見る人からの距離を考慮して決めるのが基本です。
大きすぎると設置場所に収まらず、小さすぎるとメッセージが伝わりません。体育館のステージ上や校門、フェンスなど、定番の設置場所ごとにおすすめのサイズを紹介します。
| 設置場所 | 推奨サイズ(一例) | 特徴 |
| 体育館のステージ上 | 縦90cm~120cm × 横500cm~1000cm | 式典の背景として全体が見渡せるように、横長の大きなサイズが主流です。卒業生や保護者席からもしっかり見える大きさを選びましょう。 |
| 校門・正門 | 縦120cm × 横300cm~500cm | 登下校する生徒や来校者に向けて設置します。門の幅に合わせて、記念撮影の背景にもなるようなバランスの良いサイズが人気です。 |
| 校舎の壁面・フェンス | 縦120cm~180cm × 横500cm~1000cm | 遠くからでも視認できるよう、文字も幕も大きめのサイズが適しています。設置スペースを事前に正確に計測することが重要です。 |
サイズを決める際は、必ず事前にメジャーで設置予定場所の寸法を測りましょう。また、学校によっては設置に関する規定がある場合もあるため、先生に確認しておくと安心です。
伝わるレイアウト構成とは?文字配置と余白で変わる印象
レイアウトで最も大切なのは、メッセージの視認性と伝わりやすさです。文字やイラストをただ配置するのではなく、情報の優先順位を考えて構成しましょう。
- メインメッセージは中央に大きく:「祝 卒業」「ご卒業おめでとうございます」といった一番伝えたい言葉は、横断幕の中央に最も大きく配置します。人の視線は自然と中央に集まるため、メッセージが瞬時に伝わります。
- 関連情報は控えめに:学校名、卒業年度、贈る側の名前(例:「在校生一同」)などは、メインメッセージを邪魔しないよう、四隅や上下に少し小さめのサイズで配置するのが一般的です。
- 余白を意識する:文字やイラストを詰め込みすぎると、窮屈で読みにくい印象を与えてしまいます。上下左右に十分な余白を設けることで、メインのメッセージが際立ち、全体的にすっきりと洗練されたデザインになります。
伝えたい情報を整理し、メリハリのある文字サイズと適切な余白を心がけることが、心に響く横断幕デザインの鍵となります。
フォントの選び方!卒業式にふさわしい書体とカラーの組み合わせとは
フォント(書体)とカラーは、横断幕全体の雰囲気を決定づける重要な要素です。卒業式という場にふさわしい、品格とメッセージ性を両立させる選び方を解説します。
卒業式におすすめのフォント
与えたい印象に合わせてフォントを選ぶことで、メッセージに込めた想いをより深く表現できます。
| 書体(フォント)の種類 | 与える印象 | おすすめのメッセージ |
| ゴシック体 | 力強い、はっきりしている、読みやすい | 「未来へ羽ばたけ!」「祝 卒業」など、シンプルで力強いエール。 |
| 明朝体 | 丁寧、知的、格式高い、伝統的 | 「ご卒業おめでとうございます」「感謝」など、丁寧で厳粛な雰囲気のメッセージ。 |
| 毛筆体・楷書体 | 迫力、和風、温かみ、勢い | 「祝 卒業」「夢」「絆」など、漢字一文字や短い言葉で強いインパクトを与えたい場合。 |
視認性の高いカラーの組み合わせ
横断幕の配色は、遠くからでもはっきりと文字が読める「視認性」を最優先に考えます。背景色と文字色のコントラスト(明度差)を大きくすることが基本です。
- 定番の組み合わせ:「白地に黒文字」や「白地に濃い青(紺)文字」は、最も読みやすく失敗のない組み合わせです。祝福ムードを高める「白地に赤文字」も人気があります。
- 落ち着いた印象の組み合わせ:「紺地に白文字」は、厳粛で引き締まった印象を与えます。高級感も演出できるため、式典の雰囲気にマッチします。
- 色の使いすぎに注意:使用する色は、基本的には背景色を含めて2〜3色に絞ると、デザインに統一感が生まれ、メッセージが伝わりやすくなります。カラフルにしすぎると、かえって文字が読みにくくなるため注意が必要です。
卒業式の横断幕に使われる定番の生地とは?おすすめ生地2選
横断幕を制作する上で、デザインと同じくらい重要なのが「生地選び」です。設置する場所や期間、求める仕上がりの雰囲気によって最適な生地は異なります。
ここでは、印刷業者に依頼する場合の定番生地と、自分たちで手作りする場合におすすめの生地を、それぞれの特徴とあわせて詳しく解説します。
定番の生地① 屋内外で使えるターポリン
ターポリンは、ポリエステル製の布を塩化ビニル樹脂で挟んだシート状の生地です。テントの屋根などにも使われるほど丈夫な素材で、横断幕の生地としては最も定番と言えるでしょう。耐久性、耐水性に優れているため、屋外での長期間の設置にも安心して使用できます。
卒業式のメッセージを校門や校舎に掲示し、在校生や保護者、地域の方々にも見てもらいたい場合に最適です。丈夫で汚れも拭き取りやすいため、翌年以降も繰り返し使用できます。
定番の生地② 屋内用の綺麗な発色のトロマット
トロマットは、ポリエステル100%の厚手で透けにくい布生地です。ターポリンと比べて非常に軽く、しなやかな質感が特徴。インクの吸収性が高く、写真や文字を非常に美しく表現できるため、屋内で使用する横断幕やタペストリーによく利用されます。
卒業式当日の体育館の装飾や、卒業生が記念撮影をする際の背景として使う場合に最適です。軽くて扱いやすく、折りたたんでもシワになりにくいため、保管や持ち運びにも便利です。
手作り横断幕の場合におすすめの生地とは?
クラスや部活の仲間たちと、想いを込めて横断幕を手作りするのも素敵な思い出になります。
手芸店やホームセンターで入手しやすく、加工しやすい布生地を選ぶのがポイントです。アクリル絵の具や布用ペンなどで直接文字や絵を描くのに適した生地を紹介します。
| 生地の種類 | 特徴 | 価格帯の目安 |
| ツイル | 綾織りの丈夫な生地。適度な厚みがあり、ペンキや絵の具が裏移りしにくい。比較的安価で扱いやすい。 | 安価 |
| 帆布(はんぷ) | 厚手で非常に丈夫な綿生地。耐久性が高く、しっかりとした仕上がりになる。トートバッグなどにも使われる素材。 | 普通 |
| シーチング | 薄手で平織りの綿生地。価格が安く、大きなサイズでもコストを抑えられる。薄いので、描く際は下にシートなどを敷く工夫が必要。 | 非常に安価 |
手作りの場合は、予算と作りたい横断幕のイメージに合わせて生地を選びましょう。耐久性を重視するなら帆布、コストと扱いやすさのバランスならツイルがおすすめです。布の端はほつれやすいため、ミシンで縫ったり、布用の接着剤で処理したりすると仕上がりが綺麗になります。
卒業式の横断幕をどう作る?業者依頼と手作り場合の流れを比較
卒業式の横断幕を用意する方法は、大きく分けて「専門業者への依頼」と「自分たちでの手作り(自作)」の2つがあります。予算や納期、そして横断幕に込めたい想いに合わせて最適な方法を選びましょう。
業者に依頼する場合の流れと注意点
専門業者に依頼すれば、高品質で耐久性のある横断幕を確実に作ることができます。特に屋外での使用や、長期間の掲示を考えている場合に最適です。
依頼から納品までの基本的な流れ
業者に依頼する場合、一般的に以下のステップで進みます。
- 業者選定・見積もり依頼:横断幕を制作している印刷会社や専門業者をインターネットで探し、サイズや生地、加工方法(ハトメ加工など)を伝えて見積もりを取ります。
- デザインデータの作成・入稿:IllustratorやPhotoshopなどのソフトを使い、業者の指定する形式でデザインデータを作成します。データ作成が難しい場合は、業者のデザインサポートサービスを利用するのも一つの手です。
- 注文・支払い:デザインと仕様が確定したら、正式に注文し、支払いを済ませます。
- 製作・納品:業者が印刷・加工を行い、完成品が指定の場所に届けられます。
依頼する際の注意点
業者に依頼する際は、卒業式当日に間に合うように、スケジュールに余裕を持つことが最も重要です。特に2月〜3月は卒業・入学シーズンで業者が混み合うため、早めに相談・注文しましょう。また、パソコンの画面で見る色味(RGB)と、実際に印刷されるインクの色味(CMYK)は若干異なる場合があります。色に強いこだわりがある場合は、色校正サービスがあるか事前に確認しておくと安心です。
自分たちで手作り(自作)する方法とポイント
卒業生や保護者、先生が協力して横断幕を手作りすることは、費用を抑えられるだけでなく、制作過程そのものがかけがえのない思い出になります。手作りならではの温かみのある横断幕は、式典に華を添えるでしょう。
手作りの基本的な流れ
自分たちで横断幕を制作する場合、以下の手順で進めるのが一般的です。
- 材料の準備:土台となる布、布用の絵の具や塗料、筆、マスキングテープ、下書き用の鉛筆などを準備します。
- デザイン決め・下書き:布を広げ、完成イメージを元に鉛筆やチャコペンで薄く下書きをします。プロジェクターでデザインを投影してなぞると、正確な下書きができます。
- 色塗り・文字入れ:下書きに沿って、絵の具で色を塗ったり文字を書いたりします。にじみを防ぐため、マスキングテープを活用するのがおすすめです。
- 乾燥・仕上げ:塗料が完全に乾くまで、風通しの良い場所で十分に乾燥させます。必要に応じて、布の端を三つ折りにして縫うなど、ほつれ防止の処理をします。
手作りを成功させるポイント
手作りで綺麗に仕上げるには、いくつかのコツがあります。塗料は、布にしっかり色が乗り、洗濯しても落ちにくい「布用絵の具」や「アクリル絵の具」がおすすめです。大きな文字をきれいに書くには、厚紙で文字の型(ステンシル)を作ってから色を塗ると、輪郭がはっきりして見栄えが良くなります。何より大切なのは、みんなで楽しみながら作業することです。準備から完成まで、協力して作り上げる経験は、卒業という門出の素晴らしい記念になるでしょう。
卒業式当日の設置方法と注意点
心を込めて準備した横断幕も、設置で失敗しては台無しです。卒業式当日に慌てないよう、設置方法と注意点を事前に確認し、安全かつ綺麗に飾り付けましょう。
体育館や校門など設置場所の確認
横断幕を設置する前には、必ず学校側への確認が必要です。安全確保と式典の円滑な進行のため、以下の点を確認しておきましょう。
まず、設置が許可されている場所を具体的に確認します。体育館のステージ上部や壁面、校門、フェンスなどが一般的ですが、学校によっては指定の場所があったり、景観や安全上の理由で設置できない場所があったりします。また、設置可能な時間帯(式典の前後など)や、壁や床を傷つけないための養生の要否、使用して良い道具(テープや釘の使用可否など)についても事前に聞いておくとスムーズです。屋外に設置する場合は、強風で横断幕が飛ばされたり、通行の妨げになったりしないか、周辺の安全にも配慮しましょう。
【場所別】安全に横断幕を設置するための道具と手順
設置場所によって必要な道具や手順は異なります。特に高い場所での作業は危険を伴うため、必ず2人以上で安全に十分注意して行ってください。
| 設置場所 | 主な道具 | 設置手順と注意点 |
| 体育館の壁面・ステージ上部 | ロープ(紐)S字フック脚立 | ステージ上部のバトン(吊り下げ用のパイプ)や壁面のフックを利用します。脚立を使う際は、必ず補助者が支え、安定した足場で作業してください。横断幕の上部のハトメ(紐を通す穴)からロープを通し、左右均等な力で引っ張りながら結びつけ、シワやたるみが出ないように調整します。 |
| 校門・フェンス | ロープ(紐)結束バンドはさみ or カッター | 屋外は風の影響を受けやすいため、ハトメ1つ1つをフェンスの支柱などにしっかりと固定します。風でバタつかないよう、上下左右を強めに引っ張りながら固定するのがポイントです。結束バンドを使うと簡単にしっかりと固定できます。通行の妨げにならない高さや位置に設置しましょう。 |
| 手持ち(記念撮影用) | 軍手(任意) | 卒業生や保護者、先生方と記念撮影する際に使用します。複数人で横断幕の両端を持ち、地面と平行になるように高さを合わせます。文字が隠れたり、端が垂れ下がったりしないように、全員で息を合わせてピンと張りましょう。 |
設置が完了したら、少し離れた場所から見て、傾きやたるみがないか最終チェックをしましょう。式典終了後は、学校の指示に従い、設置時と同様に安全に注意しながら速やかに撤収してください。
まとめ
アドマクではオリジナル横断幕・懸垂幕・垂れ幕のデザイン制作を承っております。ご利用用途やサイズから費用を自動見積もりをすることもできますので、ぜひご確認ください!